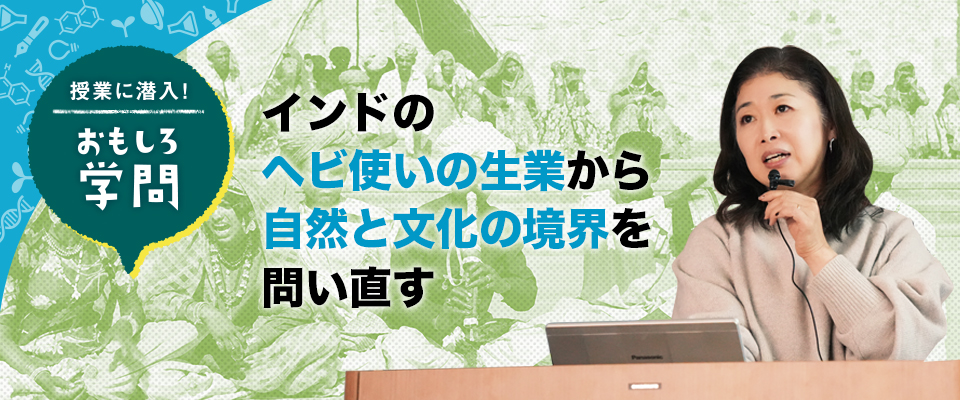
2025年春号
授業に潜入! おもしろ学問
岩谷彩子
国際高等教育院 教授/人間・環境学研究科併任
異なる社会に生きる人々の世界に身を置くことで、自文化が前提としている価値観を見直したり、「人類に共通するものは何か」を探究したりする学問・文化人類学。近年は人間中心的な考えを反省し、動物や植物、道具や建物などの「モノ」や「環境」からの働きかけを積極的に評価する「マテリアル・ターン」と言われる動向が注目されている。人間が具体的なモノや環境と結ぶ関係をつぶさに追えば、当たり前だと思っていた概念や世界観が大きく揺らぎだす。
この授業では、「主体/客体」、「精神/身体」、「自然/文化」などの二項対立を特徴とする近代的な思考を再考する視点として、近年の文化人類学の研究を紹介してきました。今日のテーマは「動物と人間との関係の再考」です。動物と人間の関係を巡っては、これまでに様々な議論がありました(❶)。今日のお二人の発表でも、その関係が簡単には割り切れないことを実感したと思います。

今回の講義では、北西インドのラージャスターン州でヘビ使いを生業とする「カールベーリヤー」という遊芸民を取り上げ、動物と人間がどのような関係を形成し、その関係がどう変化してきたのかを考えてみましょう。
人間中心主義的な自然観・世界観を批判する人類学の新たな潮流
カールベーリヤーの「カール」は「黒」を意味しており、「黒いコブラや黒いヘビを操る人々」としてこう呼ばれます。インドのヒンドゥー社会では動物を扱う人たちの地位は総じて低く、かつてカールベーリヤーは「不可触民」と呼ばれていました。彼らは移動生活をしていましたが、近年は村に簡単な家を作って居住しています。
カールベーリヤーの生業は大きく分けて三つあり、その一つがヘビに関する仕事です。プーンギーという竹笛の演奏に合わせて、かごの中のヘビが踊るヘビ使いの見世物が有名です。他にもヘビの駆除やヘビに噛まれた際の治療、ヘビの猛毒を原料とした薬の販売をしていました。
なぜ毒を持つヘビに関する生業が成立したのか。その背景には、恐ろしい力を持つ存在は、同時に恵みをもたらす聖なる存在でもあるとみなすヒンドゥー教の世界観があります。例えば、シェシャナーグというヘビの王様は千の頭を持ち、宇宙の全ての惑星を首で支えているとされています(❷)。また、インド三大神の一つであるシヴァ神は常にコブラと一緒に描かれます(❸)。

❷ シェシャナーグ

❸ シヴァ神

❹ カニーパー・ナート

カールベーリヤーが先祖とみなすカニーパー・ナートという行者(❹)には、ヘビにまつわるこんな伝説があります。ゴラクナートという著名な行者に「望む食べ物を何でも差し出そう」と言われたカニーパー・ナートは、無理難題を吹っ掛けようとヘビの毒を所望したところ、本当に毒が出てきてしまった。収拾がつかなくなって仕方なく毒を飲んだところ、神様がその勇気に免じてカニーパー・ナートとその子孫たちにヘビの毒に侵されない力を与えたとされています。
ところが1972年にインド野生生物保護法が成立し、ヘビに関する仕事ができなくなります。自然保護の精神に基づき、人間に害がある動物や科学・教育を目的とする場合を除いて、野生生物や森林の植物の捕獲・採取が禁止されたのです。ヘビやコブラも対象になり、ヘビ使いをしているのが見つかると罰金または禁固刑に処されてしまうようになりました。
野生生物保護法下では、狩猟で得た動植物を私的に所有・販売するには政府の許可が必要です。つまり、「野生生物は政府の所有物である」という新しい自然観が持ち込まれたのです。カールベーリヤーたちは、女性は歌や踊り、男性は砕石や土木作業などの日雇い労働に従事しはじめ、生活様式も移動生活から半定住生活に変化しました。
ヘビ使いができなくなった頃、新たな生業として、ヘビではなく女性が踊る芸能が生まれました。当初は彼らのコミュニティ内だけで披露されていたこの踊りは、ラージャスターン州の観光局に見出され、観光客相手に舞台で披露されるようになり、今では「カルベリア・ダンス」と呼ばれて世界各地でワークショップが開催されるほど有名になりました(❺)。
有名になるにつれて衣装が大きく変化し、スパンコールのついた黒色の衣装を纏うようになりました。この衣装を着て回りながら踊るダンサーは、ヘビがとぐろを巻く姿を連想させます。背を大きく反らせて瞼でお札や指輪をキャッチするなど、踊りにもエンターテインメント性が盛り込まれました。
カルベリア・ダンスは、2010年にはユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、インドを代表する民俗芸能に発展。女性がヘビの動きを模倣して、黒いスカートをひらめかせて旋回しながら踊る姿が、「人間と自然界との相互の結びつき」を体現しているとして、選考されました。
最近の踊りで特に注目してほしいのが、ヘビの鎌首を模したポーズです。実は、このポーズはインドの国民的娯楽であるボリウッド映画から採り入れられました。このヘビの鎌首ポーズはバラタナティヤムという古典舞踊に由来するのですが、そのポーズが映画を通してカルベリア・ダンスに取り込まれています。カルベリア・ダンスが誕生したのは野生生物保護法が発令されたのと同時期。現在活躍するダンサーはヘビがいない日常で踊っているにもかかわらず、映画に登場するヘビのイメージを踊りに取り込んだのです。

ヘビ使いの見世物

1980年代のカルベリア・ダンス

近年のカルベリア・ダンス
最後に、カールベーリヤーの例から「自然/文化」の境界について考えてみましょう。インドでは、ヘビは毒を持つ危険な動物である一方で、福ももたらす両義的な存在です。そのヘビを扱う力を持つとされるカールベーリヤーは社会のなかでマイノリティであり、動物の殺生や呪術的な治療など特殊な役割を担ってきました。
ところが野生生物保護法が制定され、カールベーリヤーはヘビとの直接的な接触の機会を絶たれました。同時に、禁じられたヘビとの関係は新たに「カルベリア・ダンス」を生みました。その舞踏は自然との連続性を失わない独自の文化として無形文化遺産に登録されましたが、他方でヘビ使いが演奏した竹笛のプーンギーや自然との関係を歌う歌、薬草に関する知識は姿を消しつつあります。

野生生物保護法はヘビを守るもの、無形文化遺産はカールベーリヤーの文化を守るものとして、インド社会に持ち込まれました。そこでは自然と文化ははっきりと分けられています。ですが、ヘビに関する生業は、管理・保護される「自然」や、自然とは区別される「文化」という枠組みではないところで成立してきたのではないでしょうか。
西洋社会に由来する自然保護、文化保護の視点では、カールベーリヤーのあり方を理解することはできません。両義的な存在としてインドの世界観や生業を生成してきたヘビやカールベーリヤーに学ぶことで、私たちに染み着いた「自然/文化」を振り分ける二元論的な視点を問い直すことが重要ではないでしょうか。
「文化人類学Ⅱ」では、各授業の冒頭に学生による発表と議論を実施。「イメージと『もの』」、「食べられるものと食べられないもの」など、12のテーマから1つを選んで発表する。この日は「動物と人間のあいだにあるもの」をテーマに2人の学生Aさん・Bさんが発表。身近な題材をもとに活発な議論が巻き起こった。
Aさんは、「馬は人間社会においてどんな役割を担ってきたか」に着目。神戸・六甲山牧場に遊びに行った経験に触れ、野生動物としての馬と触れ合う体験が楽しまれている一方、馬は人工的な環境下に絡めとられていると指摘。現代社会では多くの動物が人間の管理下におかれ、自然と文化の境界が曖昧になっているのではないかと指摘した。

Bさんは、他人のペットを傷つけると器物損壊罪にあたることを取り上げ、「動物はあくまで『モノ』として扱われるのか、あるいは人間と対等の権利をもつのか」と問題提起。受講生からは、「動物を人間と対等に扱うと、畜産業が成り立たなくなるのでは」などと、様々な意見が飛び交った。

いわたに・あやこ
1972年、鳥取県に生まれる。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程を修了。広島大学大学院社会科学研究科などを経て、2023年から現職。専門は移動民・ロマの研究。
>> 国際高等教育院