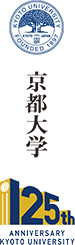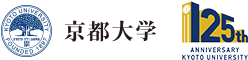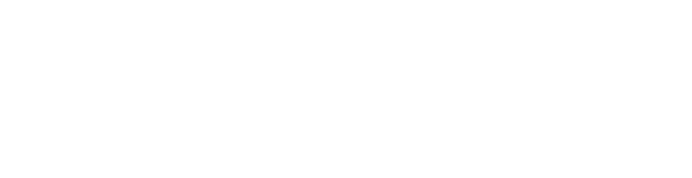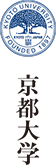メンバー誰もが未経験のなかでの
NHK学生ロボコンで全国制覇の快挙!
勝利を引き寄せた“個の力”。
京都大学機械研究会
京大唯一のロボット製作サークル。「自発的なものづくり」の活動理念のもと、ハード製作、電子工作、プログラミングなどを中心に活動。学祭での展示のほか、全国のコンテストで実績多数。
バラバラのメンバーが団結し、頂点に挑む。
2019年のNHK学生ロボコンで並み居る強豪を押しのけて全国制覇、モンゴルで行われた世界大会ABUロボコンへ駒を進め、ベスト8という結果を残した京都大学機械研究会。NHK学生ロボコンへの参加は15年ぶり、メンバー全員が未経験という状態から快挙を成し遂げた主要メンバー3名にお話を伺いました。

NHK学生ロボコンの会場での一枚。競技は2体のロボットによる連携がものを言うタイムトライアル。本番直前まで念入りに調整を繰り返す。

さらに改良を重ね、タイムを大きく縮めて挑んだABUロボコン。前列左から2番目が北村さん、5番目が松本さん、後列左から5番目が岡本さん。
北村健浩さん(工学研究科修士課程1年生)
ロボコン出場を目的とした他大学のサークルと違い、機械研究会はものづくり好きのゆるい集まりです。普段は個人個人がバラバラに活動していますが、NHK学生ロボコンに出てみたいと呼びかけるとサークルの半数にあたる10人強が関わることに。私が3年生だった2018年10月から本格始動して、2019年8月のABUロボコンまでノンストップでした。
今回の学生ロボコンはフィールド上の障害物を乗り越えたり、ブロックを投擲したりと複雑な動きが要求されるタイムトライアル競技。私が担当したのはロボットのハード面の設計・制作です。過去大会の動画を観察してゼロから研究しました。設計コンセプトは『とにかくシンプルに』。スピードでは強豪校に敵いませんが、ミスを少なく抑えられたのが勝因でした。
ABUロボコンはベスト8という結果でしたが、力は尽くせたと思っています。おかげで学内でも機械研究会が注目されるようになったので、それが後輩たちの活躍につながれば嬉しいですね。
大舞台でもブレない自分の軸を持ち、過程を最大限に楽しむことができる力。
松本直樹さん(工学部4年生)
機械研究会で学生ロボコンに参加するという話が出たのは僕が2年生の時。ちょうど時間に余裕のある時期だったので「面白そうだな」というぐらいの気持ちでソフトウェア担当として参加したのですが、始まってみると困難の連続でした。
最初の壁は、誰もロボットを作るノウハウを持っていないということでした。議論をしても話がまとまらず、先の見えない不安な時期が続きました。それを乗り越えると、次は過酷な練習環境が待っていました。サークル棟の屋上に仮設フィールドをつくったのですが、夜は寒さに手がかじかみ、昼は直射日光でフラフラに……。そんな苦労も学生ロボコン本戦出場、まさかの優勝という結果で報われました。
ABUロボコンを振り返ってみると、他国のチームと交流できたことが刺激的でした。会場だけでなく滞在先のホテルでも夜遅くまで議論を交わし、世界は広いけど負けてたまるかという気にさせられましたね。これからも周囲の人たちから刺激を受けつつ、面白いものをつくっていきたいです。
自分の「好き」に全力を注ぎ、他人の「好き」から刺激を受けるクリエイティブな人間力
岡本尚之さん(工学部4年生)
僕はもともと機械研究会のメンバーではありませんでした。2年生のときに学生ロボコンのメンバーに誘われて参加したものの、何をすればいいのか誰も教えてくれないんです。ソフトウェア関係でできることは片っ端からやってみて、最終的にロボットハンドの制御に落ち着きました。最後まで不安だったのはブロックを投擲する動作の制御ですね。練習でうまくいったとしても本番環境でどう転ぶか予想がつかないので、極力すぐに調整できるようなソフトウェアをつくり、本番直前に調整することで乗り切りました。
初出場でこれだけの成績を残せたのは、ものづくりの素質がある人が機械研究会に吸い寄せられて来るからじゃないでしょうか。好きに作っていいということを売りにしているから、ものづくりを突き詰めた人が最終的にたどり着く場所になっている。そんな個人の力が一つの方向でまとまったことが、結果につながったのだと思います。
一人ひとりの熱中が大きな成果を生み出す、“スタンドプレーから生じるチームワーク”の力